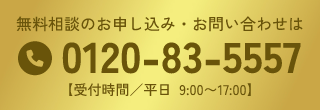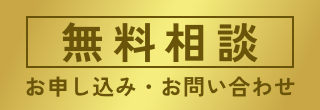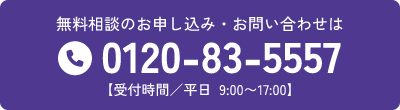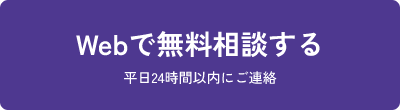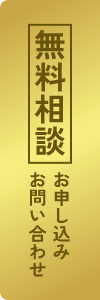遺言書作成
「残された家族に、自分の想いを伝えたい」
「相続で揉めてほしくない」
そう願うなら、遺言書を作成しておくことが最善の対策です。
遺言書とは、もしもの時に備えて、ご自身の財産を「誰に、何を、どのくらい相続させるか」を事前に決めておくための書面です。
遺言書がない場合、相続が発生すると、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして、財産の分け方を決めなければなりません。
しかし、遺言書があれば、その内容に沿って遺産を分けることができるため、この協議が不要になります。
これにより、相続人同士の不要なトラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現することができます。
ただし、遺言書は民法の定める形式や内容に沿っていなければ、法的な効力が認められません。
ご自身で作成される際は、注意が必要です。
岡崎相続サポートセンターでは、ご依頼主様の想いを第一に、トラブルの起きにくい、確実な遺言書の作成をサポートします。
遺言書を作成するメリット
ご自身の意志を反映できる
法定相続では、遺産の分け方が民法で定められています。
しかし、遺言書があれば、法定相続よりも遺言の内容が優先されるため、ご自身の想いや意向を遺産分割にそのまま反映できます。
法定相続人以外にも財産を分けられる
遺言書がない場合、法定相続人(配偶者、子、兄弟など)以外の方が財産を受け取ることはできません。
しかし、遺言書に記載することで、お世話になったご家族や内縁の妻など、法定相続人以外の方にも財産を遺すことが可能です。
家族のトラブルを回避できる
遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要がなくなります。
これにより、財産の分け方を巡る親族間の争いを回避し、円満な形で手続きを進めることができます。
遺言書の種類と特徴
遺言書には主に3つの種類があります。
1. 自筆証書遺言
ご自身で全文、日付、氏名を自筆し、捺印することで作成できます。
費用がかからず、内容を秘密にできるというメリットがありますが、形式の不備で無効になったり、発見されなかったり、改ざんされたりするリスクがあります。
また、開封時には家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。
2. 公正証書遺言
2人以上の証人とともに公証役場へ行き、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、作成してもらう方法です。
公証人が内容を確認するため、不備がなく確実な遺言書を作成できる点が最大のメリットです。
また、原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配がなく、家庭裁判所での検認も不要です。
ただし、作成費用がかかります。
3. 秘密証書遺言
遺言書の存在のみを公証人に証明してもらう方法です。
内容を秘密にできる一方で、形式不備で無効になるリスクや、紛失・未発見のリスクがあります。
開封時には検認が必要です。
岡崎相続サポートセンターでは、安全性と確実性の観点から、公正証書遺言での作成をおすすめしています。
公正証書遺言の作成手順
当センターがご依頼をいただいた際の、公正証書遺言作成サポートの流れをご紹介します。
1. 初回相談(要予約・60分無料)
まずは、お客様のご要望や現在の状況を丁寧にお伺いします。
「どんな想いで遺言を書きたいか」「どのように財産を分けたいか」など、お気持ちをしっかり受け止めます。
2. 相続人・財産の確認
相続人や受遺者の確認、所有されている財産の種類と評価額を把握します。
これにより、後々トラブルになりやすい遺留分の問題も考慮した上で、効果的な内容を提案します。
3. 遺言書の原案作成
お客様の意向を最優先し、専門家の視点からアドバイスを加えながら、遺言書の原案を作成します。
4. 公証役場との調整
公証人との内容確認や、公証役場での手続きのスケジュール調整も当センターが代行します。
5. 遺言書作成
2人以上の証人とともに公証役場へ行き、公証人の立会いの下、遺言書を作成します。
証人がいない場合も、こちらで手配いたしますのでご安心ください。
もし遺言書が出てきたら
故人の遺品整理などで遺言書を発見したら、絶対に開封しないでください。
特に、公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要と民法で定められています。
検認を経ずに開封してしまうと、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
複数の遺言書が見つかった場合は、日付が最も新しいものが有効とされます。
どの遺言書も開封せず、すべて家庭裁判所に持ち込んで判断を仰ぐ必要があります。
岡崎相続サポートセンターでは、発見された遺言書の検認手続き、その後の遺言執行(遺言の内容を実現する手続き)まで、一貫してサポートいたします。
「遺言書を書こうかな」と思った時が、一番のタイミングです。
まずは、無料相談をご利用ください。
土日もご相談可能です(要予約)。