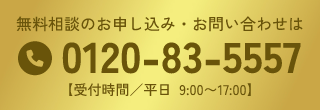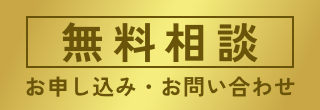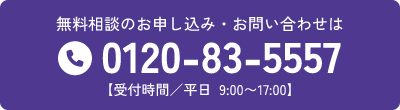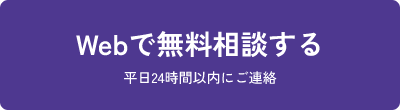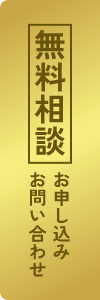預貯金等の相続手続き
ご家族が亡くなられた後、故人名義の預貯金口座は原則として凍結され、入出金ができなくなります。
これは、相続人同士の無用なトラブルを防ぐため、金融機関が行う措置です。
預貯金の払い戻しや名義変更を行うためには、所定の相続手続きが必要となります。
岡崎相続サポートセンターでは、煩雑な金融機関とのやり取りや必要書類の収集をサポートし、預貯金の相続手続きをスムーズかつ円滑に完了させます。
口座凍結と手続きの必要性
なぜ口座は凍結されるのか?
金融機関が名義人の死亡を知ると、預金口座は直ちに凍結され、取引が制限されます。
口座は一時的に「相続人全員の共有財産」となり、遺産分割協議で誰がどれだけ取得するか決まるまで、単独での引き出しはできなくなります。
【注意点】
凍結前の引き出しリスク
金融機関が死亡を知る前に預金を引き出した場合、他の相続人とのトラブルになる可能性があります。
また、故人に借金がある場合、引き出し行為が「相続を承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクが生じるため、慎重な判断が必要です。
預金相続の2つの方法
預金の相続手続きには、主に以下の2つの方法があります。
預金の払い戻し(解約)
故人の口座を解約し、遺産分割協議で決まった割合に基づき、各相続人の口座へ現金を振り込む方法です。
一般的に多く選ばれます。
口座の名義変更
故人の口座を解約せず、相続人のうちの一人の名義に変更する方法です。
高利率の定期預金など、解約で利息を失いたくない場合に選択されることがあります。
預金相続手続きの5つのステップ
預金の払い戻し(解約)を行う場合の一般的な手続きの流れは以下の通りです。
ステップ1:金融機関への連絡と残高証明書の取得
故人の口座があるすべての金融機関に相続の発生を連絡し、口座を凍結してもらいます。
同時に、亡くなった日時点の「残高証明書」の発行を依頼します。
これは遺産分割協議や相続税申告に必須の書類です。
ステップ2:遺言の有無と相続人の確定
遺言の有無を確認します。
遺言があれば、原則としてその内容に従います。
相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など、必要な戸籍を収集します。
ステップ3:遺産分割協議の実施(遺言がない場合)
遺言がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い(遺産分割協議)、その結果を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書には、誰がどの預金を取得するのかを明確に記載する必要があります。
ステップ4:必要書類の準備・提出
金融機関所定の「相続手続依頼書」を含め、必要な書類をすべて揃えます。
書類を金融機関に提出します。
この際、戸籍謄本や印鑑証明書などの原本は、他の手続きにも使用するため返却を依頼しましょう。
ステップ5:預金の払い戻し
提出した書類に不備がなければ、1〜2週間程度で、指定した相続人の口座へ払戻金が振り込まれます。
遺産分割前の預金仮払い制度
遺産分割協議が長引き、当面の生活費や葬儀費用の支払いに預金が必要になった場合でも、相続人全員の合意を得なくても、一定額を上限に単独で預金を引き出すことができる仮払い制度が利用できます。
引き出し上限額
相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分 ただし、金融機関ごとに150万円が上限となります。
この制度を利用することで、相続人全員の協力を待たずに、緊急に必要な資金を確保できます。
当センターのサポート内容
預貯金の相続手続きは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、金融機関ごとの書式対応など、非常に手間と時間がかかります。
岡崎相続サポートセンターでは、お客様の負担を軽減し、手続きを円滑に進めます。
戸籍の収集代行
生から死亡までの複雑な戸籍収集を代行し、相続人確定をサポートします。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の結果を、金融機関が確実に受理するよう、不備のない書式で作成します。
金融機関への対応
複数の金融機関にわたる手続きを一括で代行し、書類提出や照会対応の負担を軽減します。
預金相続の手続きに期限はありませんが、長期間放置すると相続関係が複雑化し、手続きがさらに煩雑になるリスクがあります。
まずは無料相談をご利用いただき、速やかな手続き着手をご検討ください。